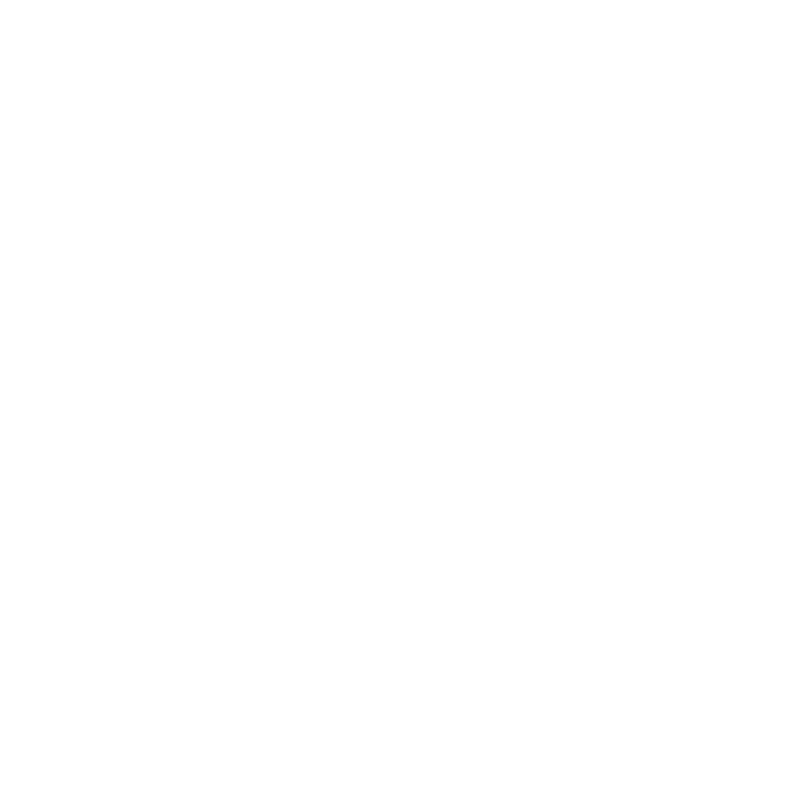
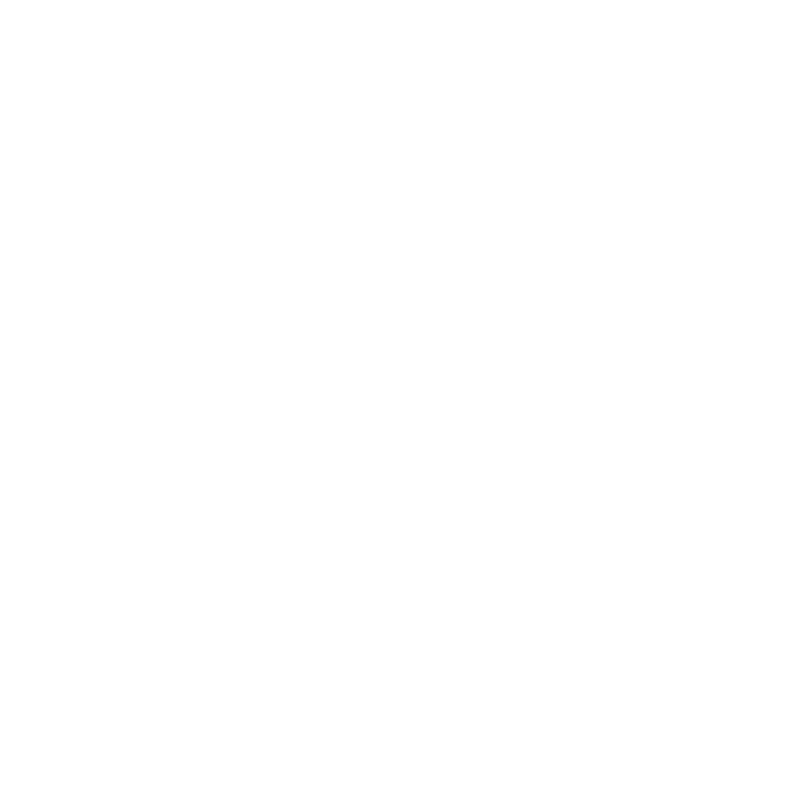
酵母が美肌づくりに効果的なのをご存知ですか?
酵母化粧品には美肌に導くとされる成分が豊富に含まれている為、毎日のスキンケアに効果的です。
酵母は食の分野では身近なものだと思いますが、化粧品に用いることでどのような効果をもたらすのかといったことは案外、世間一般的に詳しくは知られていないのが現状。
私達は酵母化粧品の素晴らしさを多くの方々に、
「知ってもらいたい」
「共有したい」
と思っています。
このページをご覧になったお客様に、少しでも「酵母」を身近に感じて頂けたら幸いです。
現在、世界中にいたるところで各地の特色のある発酵食品が食されています。その多くの発酵食品は諸説ありますが各地で偶然の産物として生まれたものが多いようです。
例えば最も古いといわれている発酵食品のルーツとしては、今から5000年前、アラビアの遊牧民が乾燥したヤギの胃袋で作った水筒にミルクを入れて大移動していました。喉の渇きを癒すために、何日か経ったミルクを飲もうと水筒を開けると、中には透明の液体と白い塊がありました。遊牧民たちはその塊を少し口にしてみると、酸味があり独特の味わいだったそう(現代のヨーグルト)。これが発酵食品誕生の起源ではないかといわれています。
それ以外にもワインの場合には、人類よりも古くから自生していたといわれるブドウの木から実が地面に落ちて潰れ、果皮に付いている天然の酵母によって勝手に発酵したことがワイン誕生のきっかけになったといわれます。その後、潰れたブドウがヨーロッパで本格的にワイン製造されるまでに至ったそうです。
また、日本における代表的な発酵食品である納豆のルーツは、諸説ありますが、弥生時代に始まった大豆などの豆類の栽培。ふだんは煮て食べられていたよう。その時代の住居の中には炉があり暖かく、床には藁や枯れ草が敷かれていました。暖まった住居の中で、敷いた藁に煮た大豆が偶然落ち、そのまま放置。自然に発酵して納豆になったという説があります。
また、こんなユニークな説もあります。聖徳太子が愛馬に煮豆をエサとして与えていたそう。余った煮豆をもったいないと藁に包んで置いておいたら自然に発酵し、食べてみたら非常においしく、それを民衆に広めたというエピソードもあります。
いずれも偶然の産物から発生し、先人たちが試行錯誤を経て現在の発酵食品の形になっているということが言えると思います。
そして、この偶然の産物が生まれるには、その土地の気候や風土が大きく影響しました。自然界にいる微生物が食材に付着し、時間が経過することで、独特な味わいと風味を生み出してきました。
発酵食品はニオイや酸味が強いのが特徴ですし、いちばん最初に口にしてみた人はかなりの勇気を持って食べたのでは、と想像できます。
その後、先人たちの試行錯誤によって、今では当たり前に冷蔵庫に並ぶ味噌や醤油、納豆、漬物、チーズ、日本酒、ワインなどの食品に生まれ変わり、世界各地で伝統的に受け継がれている食文化を形成しています。
そう考えると普段身近な発酵食品を食べるときも感慨深いものがあると感じるのは私だけでしょうか。
偶然の産物として世界各地で生まれた発酵食品ですが、その後さまざまな土地で独自の進化を遂げて現在の形になっているようです。身近なものから、聞いたことがないものまで、世界中には様々な発酵食品が存在します。その一部をまとめてみました。
| 納豆(日本) | 大豆を納豆菌(枯草菌)で発酵させたものです。 |
|---|---|
| テンペ(インドネシア) | 大豆をテンペ菌で発酵させたものです。 |
| 腐乳(中国・台湾など) | 大豆から作る豆腐にケカビまたはクモノスカビ類を付け、塩水に浸けて発酵させたものです。 |
| 豆腐よう(沖縄) | 大豆から作る豆腐を泡盛に浸けて、紅麹菌で発酵させたものです。 |
| 臭豆腐(中国・台湾など) | 大豆から作る豆腐を植物と石灰の発酵液に浸けて風味を付けたものです。 |
| パン(中東・ヨーロッパ) | 小麦をパン酵母で発酵させたものです。 |
| 葛餅(日本) | 小麦を乳酸菌で発酵させたものです。 |
| 醤油(日本) | 大豆を麹菌、酵母菌、乳酸菌で発酵させたものです。 |
|---|---|
| 味噌(日本) | 大豆を麹菌、酵母菌、乳酸菌で発酵させたものです。 |
| コチュジャン(韓国) | もち米と唐辛子を麹菌などで発酵させたものです。 |
| 豆板醤(中国) | そら豆と唐辛子を麹菌などで発酵させたものです。 |
| 鰹節(日本) | 鰹をコウジカビで発酵させたものです。 |
|---|---|
| 塩辛(日本) | 乳酸菌と原材料そのものがもつ酵素による酸化発酵の相互作用で作られたものです。 |
| チョッカル(韓国・北朝鮮) | 魚介類を発酵させた塩辛と類似の食品です。 |
| くさや(日本) | 発酵したくさや液に魚を漬けこみ干した干物です。 |
| 鮒寿司(日本) | 鮒など魚介類を乳酸菌で発酵させたものです。 |
| 飯寿司(日本) | 麹や麦芽を使って魚介類を米とともに発酵させたものです。 |
| シッケ(朝鮮) | 麹や麦芽を使って魚介類を米とともに発酵させたものです。 |
| 魚醤(東南アジア・東アジア) | 微生物ではなく、原材料そのものの酵素により酸化発酵したものです。 |
| ウスターソース(イギリス) | 微生物や原材料そのものの酵素により酸化発酵したものです。 |
| シュリンプペースト(東南アジア) | 微生物ではなく、原材料そのものの酵素による酸化発酵したものです。 |
| アンチョビ(ヨーロッパ) | 魚を発酵させたものです。 |
| ホンオフェ(韓国) | エイを自然発酵させたものです。 |
| シュールストレミング(スウェーデン) | 鰊を缶詰の中で発酵させたものです。 |
| キビヤック(イヌイット) | 海鳥を発酵させたものです。 |
|---|
| 漬物(日本) | 野菜を乳酸菌発酵させたものです。 |
|---|---|
| キムチ(韓国・北朝鮮) | 野菜を唐辛子、ニンニク、塩辛、塩などと共に乳酸菌発酵させたものです。 |
| ザーサイ(中国) | からし菜の変種を乳酸菌発酵させ、唐辛子、花椒などで調味したものです。 |
| メンマ(中国) | マチクの筍を乳酸菌発酵させたものです。 |
| ザワークラフト(ドイツ) | キャベツを乳酸菌発酵させたものです。 |
| ピクルス(ヨーロッパ) | 酢で自然発酵させたものです。 |
| ナタデココ(フィリピン) | ココナッツを発酵させたものです。 |
| バニラ(メキシコ・中央アメリカ) | 種子鞘の発酵により香料を得たものです。 |
| 黒にんにく | ニンニクを加湿し常温発酵させたものです。 |
| タバスコ(メキシコ) | 唐辛子を岩塩、穀物酢で発酵させたものです。 |
| ヨーグルト(中東・ヨーロッパ) | 牛乳や豆乳を乳酸菌で発酵させたものです。 |
|---|---|
| チーズ(中東・ヨーロッパ) | 牛乳や豆乳を乳酸菌で発酵させたものです。 |
| 馬乳酒(モンゴル) | 牛乳や豆乳を乳酸菌で発酵させたものです。 |
| 日本酒(日本) | 米と麹菌と清酒酵母で発酵させたものです。 |
|---|---|
| 黄酒(中国) | 米と麦麹と酒薬の酵母で発酵させたものです。 |
| ワイン(中東・ヨーロッパ) | 葡萄をワイン酵母で発酵させたものです。 |
| ビール(中東・ヨーロッパ) | 大麦の麦芽をビール酵母で発酵させたものです。 |
| シードル(ヨーロッパ) | りんごをりんご酵母で発酵させたものです。 |
| ヤシ酒(東南アジア・アフリカ) | ヤシの樹液を酵母で発酵させたものです。 |
| プルケ(メキシコ) | リュウゼツラン科の植物の樹液を発酵させたものです。 |
| 焼酎(日本) | 発酵酒の蒸留酒です。 |
| 泡盛(日本) | 発酵酒の蒸留酒です。 |
| ソジュ(韓国・北朝鮮) | 発酵酒の蒸留酒です。 |
| 白酒(中国・台湾) | 発酵酒の蒸留酒です。 |
| ウイスキー(イギリス) | 発酵酒の蒸留酒です。 |
| ウォッカ(ロシア) | 発酵酒の蒸留酒です。 |
| テキーラ(メキシコ) | 発酵酒の蒸留酒です。 |
| 紅茶(中国・インド・スリランカなど) | 微生物ではなく、原材料そのものの酵素により酸化発酵したものです。 |
|---|---|
| 烏龍茶(中国・台湾など) | 紅茶と同様で、発酵の度合が低い茶葉です。 |
| プアール茶(中国) | 紅茶と同様の酵素とコウジカビで発酵させたものです。 |
| 醸造酢(日本・中国) | 酒類が酢酸発酵したものです。 |
|---|---|
| 黒酢(日本・中国) | 米を麹菌の発酵によりアルコールにし、さらに発酵で酢酸にさせたものです。 |
| 甘酒(日本) | 米麹と米を原料とし、でんぷんを糖化させたものです。 |
| シッケ(韓国) | もち米のでんぷんを麦芽で糖化したものです。 |
| グルタミン酸ナトリウム | 糖蜜の発酵により製造されています。 |
私達の暮らしの中には、発酵と強く結びつきがあります。
例えば皆さんご存知の納豆。納豆は江戸時代には商品化が始まったと言われておりこれまでに広く親しまれてきた健康食品です。
納豆をおいしく食べるための醤油の製造が始まったのがきっかけだったという説もある程に江戸時代の朝食では、当たり前のように食べられていたそう。
そんな納豆も、発酵する原理は酵母の発酵とほとんど同じ。
大きな特徴は菌の種類で、納豆菌を使用して発酵させてる点です。
納豆はよく、健康に良いといわれるのは納豆菌によるもので、腸に生きたまま届いて、腸内で悪玉菌が増殖しにくい環境を作るといわれています。
また、発酵により、イソフラボンがアグリコンという分子に変化することもあり、このアグリコンには免疫力を増強する力があるためといわれています。
暮らしの中にも酵母、発酵、菌は互いに切り離せない縁があります。
湿度の高い日本では、蒸した穀物に繁殖する麹カビ(麹菌)によって醸し出される醤油、味噌、日本酒、焼酎、甘酒、米酢などの独特の発酵食品があります。
その中でも甘酒は伝統的な甘味飲料とされており、日本書紀には天甜酒(あまのたむさけ)という甘酒の起源とされる飲み物についての記述があります。
甘酒の成分は、ブドウ糖、必須アミノ酸群、ビタミン群など。この成分というのが病院で栄養補給のためにされる点滴の溶液と同じことから甘酒は飲む点滴と呼ばれています。
栄養満点の甘酒は江戸時代には体力回復に効果的な夏バテ対策ドリンク剤として町の人々に好まれていました。
現在、甘酒には酒粕または米麹を原材料としている2種類のバーションがあります。
ダイエットを目的にするなら砂糖で味の調節をしていない米麹の甘酒がおすすめ。
しかし、美容を目的にするなら美容効果が高い成分を豊富に含む酒粕の甘酒が効果的です。
どちらの甘酒も栄養満点なので継続的に飲み続けてるのをおすすめします。
医食同源とは、病気を治療するのも日常の食事をするのも、ともに生命を養い健康を保つために欠くことができないもので、源は同じだという考えです。
発酵食品が健康寿命を伸ばすといわれています。
健康維持と病気の問題でも、発酵の活躍が期待されています。
最近、心身の健康を保つための最も重要な臓器として腸が注目されています。腸には、免疫力強化、アレルギーの予防、血圧や血中コレステロールの低下、精神的な不調の解消など様々な働きがあり、発酵食品を食べることでその働きをより強められるのです。高齢化が進む社会で健康寿命を伸ばすために、発酵食品の摂取は欠かせない習慣です。
また病気になった時には、発酵で製造した医薬品が私たちを助けてくれます。抗ガン剤、抗ウイルス剤など、抗生物質にはまだまだ開発の余地があると言われます。
食品を発酵させる事には、
などのメリットがあります。冷蔵庫のなかった昔は保存性を上げることが特に有用でしたが、
現代では、独特の味や香り、発酵前の食品にはない栄養が高く評価されます。
特に最近は、腸内に多種多様な菌がびっしり群生している様子を表す「腸内フローラ(=花畑)」という言葉がよく聞かれ、これを整え健康に導くものとして発酵食品が注目を浴びています。
洋の東西を問わず古くから酵母・発酵と美容は近くにありました。日本酒を作る杜氏の手が白くなめらかなのは、お酒の発酵に欠かせない「酵母」の働きによるといわれ、パン職人の手がキレイなのも同じく発酵に必要な「酵母」の働きと言われています。それ以外にも、日本ではぬか漬けのぬか床をかきまわすと、手がスベスベになると言われたり、古代ローマでは皇帝ネロの妻ポッパエアが、寝る前に、発酵したパンをロバの乳に浸し、顔にあてがうことで、肌を白くやわらかく保っていたと言われています。
また、発酵食品を食べることも美容と健康につながるといわれています。例えば、米の発酵過程でできるコウジ酸には、くすみの原因となるメラニン色素を抑える作用があり、実際に化粧品にも多く使用されています。また、味噌に含まれるイソフラボン類や酒粕には、メラニンを生じさせる物質を阻害する働きがあることが見出されています。
また、納豆のネバネバ成分に含まれている「ポリグルタミン酸」には、肌が本来もっている保湿効果を高める美肌効果があると言われています。さらに、納豆には肌の代謝に関わるビタミンB群なども含まれており、美肌に欠かせないタンパク質も豊富です。
また、ぬか漬けもビタミンやミネラルが豊富であるほか、腸内環境を整える乳酸菌や酵素がたっぷりと含まれています。これが美肌につながっていくのです。大豆には、大豆イソフラボンという肌の老化を防ぐ抗酸化物質が含まれます。大豆を発酵させて作られた味噌は、大豆イソフラボンに加え、麹菌が作り出すアスペラチンという抗酸化物質が含まれていることがわかっています。
このように、発酵食品は身近な美容法として大変優れたものです。古くから各地で伝統と文化の中で健康法や美容法として「発酵」や「酵母」が脈々と受け継がれ、現在ではその効果というのが科学で実証されています。
酵母とは微生物の一種であり、微生物は地球に住む全生物の祖先です。目に見えない小さな生き物でありながら、様々な形で人の暮らしを支えてくれる微生物。
酵母は、球形や楕円形をした単細胞の微生物。糖をアルコールに変える「サッカロミセス セレビシエ」が代表格で、酒類の醸造などに用いられます。発酵時には二酸化炭素ガスが生成され、これが溶け込むとビールやシャンパンなど炭酸を含んだ酒ができます。このガスは酵母をイーストとして、パンの発酵に用いる際にも利用されます。
それ以外の微生物としては「カビ」「細菌」で、「酵母」も含めて各々が持つ特徴により分類されています。
カビは、糸状の細胞を伸ばして広がり、胞子を飛ばして拡散します。コロニー(集合体)を形成すると、お餅に生える青カビなどとして肉眼でも見られます。人間にとって迷惑な存在と思われがちですが、実は有益なものも多くあります。日本の国菌である麹菌も、抗生物質のペニシリンを産出する青カビも、この仲間です。
細菌は、3種の中で最も小さな微生物です。酵母と同じ単細胞で、性質も生存場所も多様性に富んでいます。代表格の乳酸菌は糖を乳酸に変える働きがあり、ヨーグルト、チーズなど牛乳の加工品をはじめ、漬物造りにも用いられます。他にも、納豆を造る納豆菌、お酢を造る酢酸菌などが、細菌に属します。
私たち「クー・インターナショナル」が目指したのは、肌本来の美しくなろうとする力を取り戻し、輝きに満ちた肌へと導くスキンケア。国内有数の化粧品メーカーとして長年研究してきたのは日本に古くから伝わる「酵母」を使用した化粧品成分でした。私たちが掲げたテーマは「美肌のための酵母」。
肌を紫外線や酸化などのダメージから保護する、潤いを保つ、肌の透明感を引き出すなど、様々な働きが期待できる「酵母」の研究を続け、たどり着いた酵母を私たちは「熟撰酵母」と名付けました。
その道のりは簡単ではなく、化粧品メーカーである私たちは、本当に肌によい酵母を探すところからスタート。実に10年以上の年月をかけ、500種類以上の酵母を研究して、美肌効果に優れた酵母を発見し、培養することに成功したのです。
そもそも酵母には、アミノ酸、ビタミン類、ミネラル類、多糖類、有機酸類など、肌に有用な成分が豊富にバランスよく含まれています。これまでの多くの化粧品は、お酒やパン由来の酵母の保湿力に着目し、それらの酵母から抽出したエキスを配合してきました。
「熟撰酵母」は、従来の酵母成分と違い、酵母を培養することによって得られる液体で、イメージとしてはこの酵母を育てているプールのようなもの。分裂を繰り返す酵母は、そのプールを自分にとって住みやすい環境にしようと、様々な美肌成分を放出します。つまり、「熟撰酵母」には、酵母が放出したそれらの美肌成分が凝縮されているのです。
クー・インターナショナルの独自成分「熟撰酵母」やその成分を使用した数々の化粧品は、四方を川と海に囲まれ、清らかな水に恵まれた工場で製造されています。美肌に良い酵母を最高の環境で培養するために何よりも欠かせないものは、豊かな自然なのです。
高い安全性を保つために最新の設備を駆使し、さまざまな手間をかけ、丁寧に作られている熟撰酵母の化粧品。さらに、人の手による入念なチェックを重ね、確かな商品だけをお届けしています。常に新鮮な作りたてをお届けできるクリーンな環境を守るため、工場の作業員は専用の作業衣やマスク、手袋を着用。また、工場には衛生管理のルールがたくさんあり、高い意識で作業を行っています。
企画をはじめ、研究・製造から発送まですべてを自社及び、関連会社で行えるのも製造メーカーならではです。
サッカロミセス/(ブドウ果実/ユズ果実)発酵液の他に、3種のコラーゲン、3種のヒアルロン酸など、美容成分を贅沢に配合。さらに、お肌へのやさしさを考えて不要なものをカットしています。これ1つで「化粧水」「乳液」「美容液」「クリーム」「フェイスパック」「化粧下地」の6アイテムの役割を果たします。クー・インターナショナルが誇る高品質な酵母化粧品をお試しいただけます。
